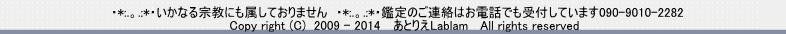トルコで紀元前6000年頃の炭化したリンゴが発見されています。また、スイスでは遺跡から紀元前2000年頃のリンゴの化石が見つかっており、その時点で既にリンゴは栽培されていたとする研究があります。16~17世紀頃になるとヨーロッパでリンゴの栽培が盛んに行われ、17世紀前半にはヨーロッパからアメリカへ持ち込まれました。
日本へは中国から最初に持ち込まれましたが、西洋から西洋リンゴが持ち込まれると日本でも西洋リンゴの方が一般的になり、それまでの種は「和りんご」と呼ばれて区別されました。
そして食用ではなく仏事用として、大規模な栽培・集荷・流通が行われていた様です。
昔からりんごは、万能な特効薬として知られていたようです。
船乗り達が遠洋航海に出る時、命がけの大仕事でした。特に食生活の偏りからくる体調の変化は深刻な問題でした。そこで、航海の際に持参したのが大量のりんごでした。壊血病等の大病防止策として、沢山りんごを食べていたそうです。また、ストレスを抱えがちな状況下でも、りんごの栄養は有効とされています。そのほか、りんごに含まれている様々な成分が、あらゆる病原を断ち切ってくれるとされています。
故事としては:*・゜・*:.。.:*
旧約聖書に登場するアダムとイヴのストリーは有名です。
蛇にそそのかされて食べた「善悪を知る果実」(禁断の果実)はリンゴだとされています。あわてて飲み込もうとしたアダムが善悪を知る果実をのどにつかえさせ、これがのどぼとけの始まりであるとの故事から、男性ののどぼとけは「アダムのリンゴ」ともいわれています。なお、食べたのがリンゴというのは後の時代に創作された俗説で、当時旧約聖書の舞台となったメソポタミア地方にはリンゴは分布せず、またその時代のリンゴは食用に適していなかったとの事です。
他にも、ギリシア神話には、「最も美しい女神に与えられる」と言われた黄金のリンゴを巡ってヘラ、アテナ、アフロディテの3女神の争いがあります。
更に近代理論科学の先駆者であるアイザック・ニュートンは、木から落ちるリンゴを見て万有引力の法則に気づいたという逸話や、ウィリアム・テルのリンゴ等があります。
|